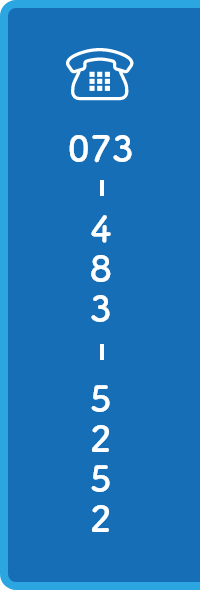【コラム】生活習慣が原因となる肝臓病をご存じですか?
お酒をたくさん飲む人がかかる病気というイメージも強い脂肪肝ですが、健康診断で指摘されても「改善方法がわからない」とそのままにしている方も多いと思います。
しかし脂肪肝の中には、アルコールとは関係なく、進行すると肝炎や肝硬変、肝がんになるリスクを含んだものがあることをご存じでしょうか。
進行しやすい脂肪肝は、生活習慣病とも深く関わりがあります。
今回は脂肪肝の中でも生活習慣が要因となって発症する非アルコール性脂肪性肝疾患について解説していきます。
生活習慣病と肝臓病の密接な関係
生活習慣病とは、糖尿病や高血圧、脂質異常症など、普段の食生活や運動習慣などが要因となって起こる体の不調の総称です。
生活習慣病は、年齢が上がるとともに発症しやすくなり、その多くには肥満が関わってきます。
肥満に加えて複数の生活習慣病が重なるとメタボリックシンドロームと診断されますが、このメタボリックシンドロームは内臓脂肪との関連が高い疾患でもあります。
そして、内臓脂肪が強く関係するのが、肝臓に中性脂肪が蓄積する脂肪肝です。
脂肪肝というと飲酒による病気というイメージがあるかもしれませんが、近年では、お酒に関係なく発症する「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」が注目されています。
非アルコール性脂肪性肝疾患が注目されている理由
前提として、非アルコール性脂肪性肝疾患は、単純性の脂肪肝と、脂肪肝から肝臓病が進行する「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」に分類されます。
単純性の脂肪肝とは、肝臓自体には負担がかかっているものの病気がほとんど進行しないものを指します。
一方で、非アルコール性脂肪性肝炎は、徐々に進行して肝硬変や肝がんを引き起こす可能性があります。
お酒による脂肪肝かと思っていたら、知らず知らずのうちに肝臓病が進行していた、というケースも少なくありません。
そういったリスクを防ぐためにも、非アルコール性脂肪性肝疾患の診断を受けた際には定期的に検査を受けることが大切です。
非アルコール性脂肪性肝炎とそれ以外の見分け方
非アルコール性脂肪性肝炎は、自覚症状や簡単な検査で見分けることは難しいのが現状です。
そのため、クリニックでは問診と血液検査の結果のスコアリング、必要に応じてエコー検査をしたり、MRI検査などを行ったりして検査結果から総合的に判断をすることが一般的です。
近年は、肝臓の硬さの程度を判定することができるエコー検査機器が登場したことで、より正確な診断が行えるようになりました。
とはいえ、確定診断をするためには肝臓の組織を少し取って病理検査をする肝生検が必要です。
肝臓病にならないための生活習慣とは
肝臓病を防ぐためにも、生活習慣を整えることが重要です。
生活習慣には食事、睡眠、運動など、さまざまな要素があります。
肝臓病を予防するために改善しなくてはならない点は人によって違ってきますので、医師と相談しながら改善点を洗い出していくことから始めましょう。
健康診断で生活習慣病の項目に該当するのは、血糖値や血圧、コレステロールなどがあります。
例えば血糖値が高い場合には、糖尿病のリスクが高くなります。
糖尿病になると動脈硬化が起こりやすくなったり、合併症によって失明や腎臓疾患を引き起こしたりとさまざまな問題につながります。
糖尿病の多くは、原因として食生活の乱れと運動不足が隠れています。
しっかりと野菜を食べること、間食を控えること、適度なウォーキングなど有酸素運動の習慣をつけることで改善できるでしょう。
肥満は肝臓への負担にも直結するため、生活習慣病のリスクが高い方は体重の見直しをすることも大切です。